診療実績(がん種別)
当センターにおける1970年から2006年までのがん種別診療実績(生存率の全国統計との比較,生存率の年代別比較,症例数の推移など)を、グラフにコメントを添えて紹介します。
- 下咽頭がん
- 舌がん
- 中咽頭がん
- 甲状腺乳頭がん
- 喉頭がん
- 食道がん
- 肺がん
- 胃がん
- 結腸がん
- 直腸がん
- 肝・胆・膵がん
- 乳がん
- 子宮頚がん
- 子宮体がん
- 卵巣がん
- 膀胱がん
- 前立腺がん
- 骨悪性腫瘍
- 軟部悪性腫瘍
- リンパ腫・白血病・多発性骨髄腫・骨髄異形成症候群
- 内視鏡検査・治療
- IVR治療
下咽頭がん
(頭頸部外科部)
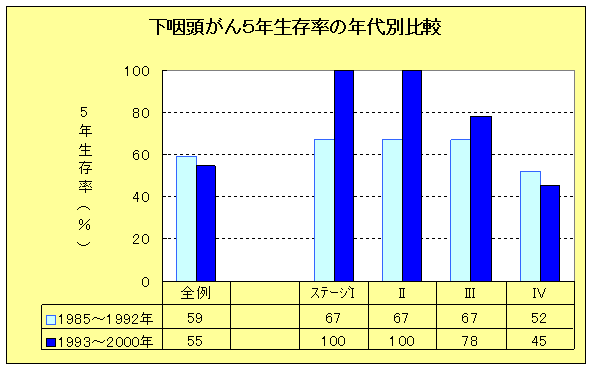
下咽頭がん手術治療例の成績です。
下咽頭がんは頭頸部がんの中でも予後不良で、一般的にその5年生存率は30%から40%です。
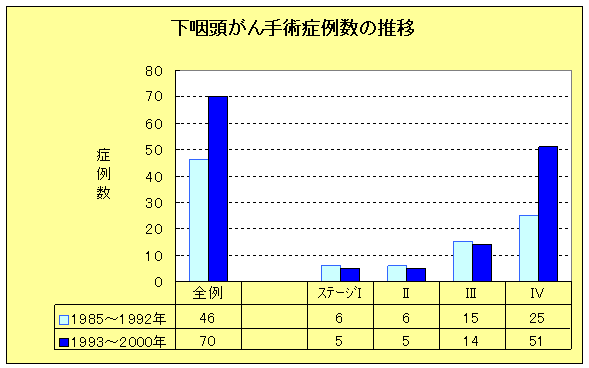
下咽頭がんはリンパ節転移が多く、そのためステージIIIまたはIVの進行例が多いのが特徴です。中高年男性で、長い飲酒および喫煙歴の方に発生しやすいです。
舌がん
(頭頸部外科部)
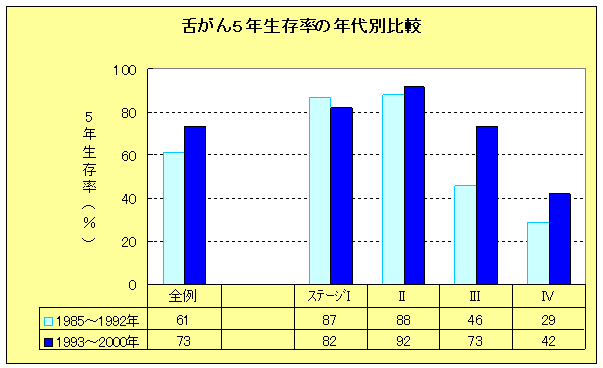
舌がん手術例の治療成績です。
リンパ節転移の有無が治療成績に最も影響します。そこで、ステージIおよびIIの方の予後は良好です。また、近年再建術の進歩により進行例においても機能と予後の改善が得られています。そこで全体の治療成績も向上しています。
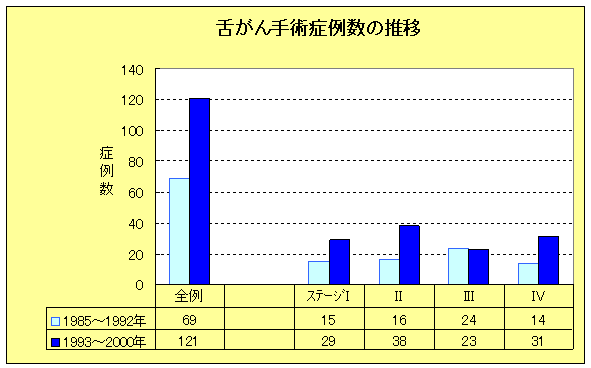
舌がんは喉頭がんと同様に、比較的早く発見されます。そのためステージIとIIの早期例が多く、それが全体の予後に反映しています。
中咽頭がん
(頭頸部外科部)
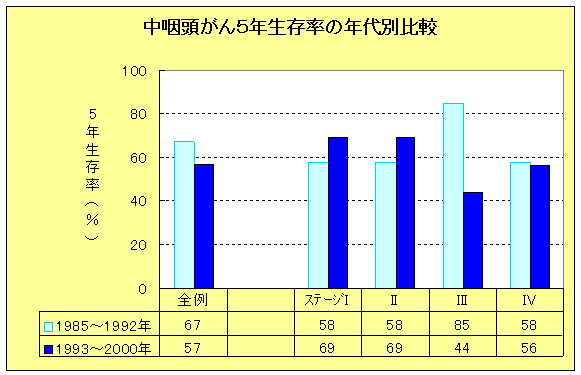
中咽頭がんの外科、放射線、化学療法の治療成績です。
近年、原発部位は化学放射線療法により形態の温存を図る例が多くなっています。
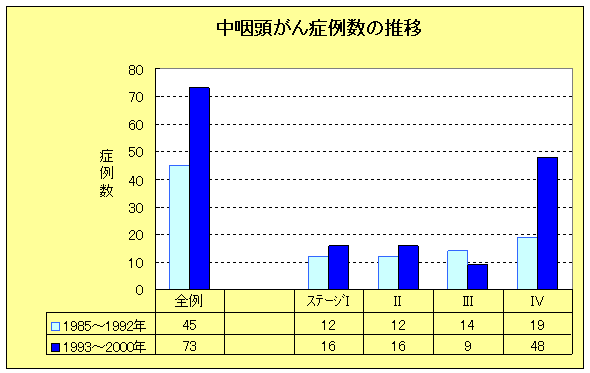
全体としては増加傾向にあります。
中咽頭がんは下咽頭がんと同様に長い飲酒歴のある中高年の男性に多い特徴があります。リンパ節転移も高率で、進行例が多い傾向があります。
甲状腺乳頭がん
(頭頸部外科部)
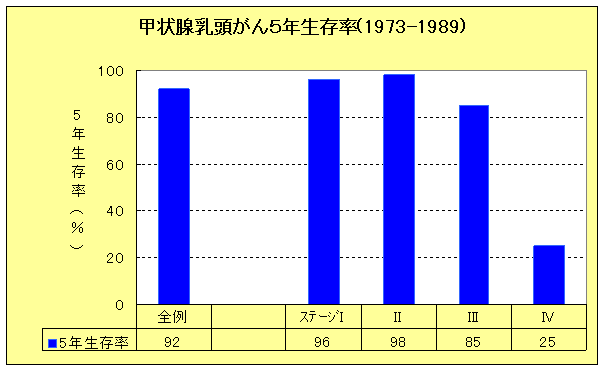
甲状腺乳頭がんは全体としては予後は良好ですが、ステージIVはやや不良です。
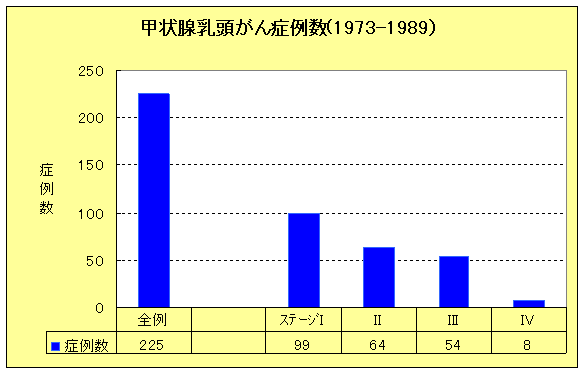
甲状腺乳頭がんステージIとIIの早期例が多い傾向にあります。
これらの予後は良好です。
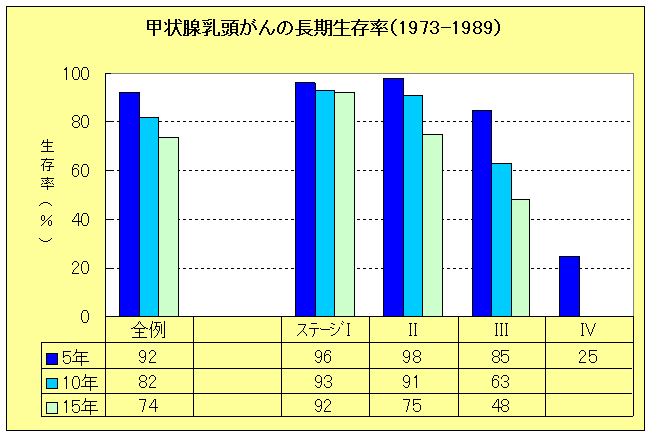
甲状腺乳頭がんの予後は全体として良好です。
早期例の生存は長期にわたり良好ですが、進行例の長期生存は早期例に比べてより低下します。
喉頭がん
(頭頸部外科部)
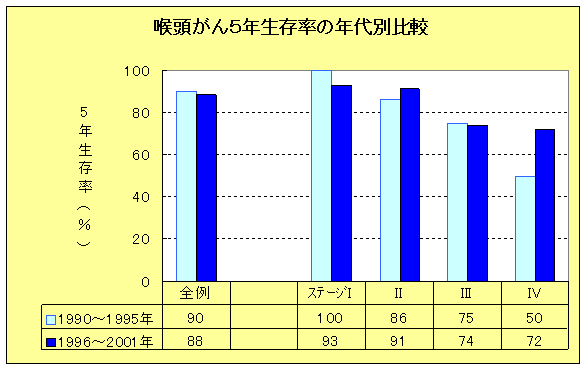
喉頭がんの外科、放射線、化学療法の治療成績です。
1990-1995年はIとIIには放射線治療が、IIIとIVには近年、T3/4の進行喉頭がんにおいても化学放射線療法により形態の温存を図る例が多くなっています。
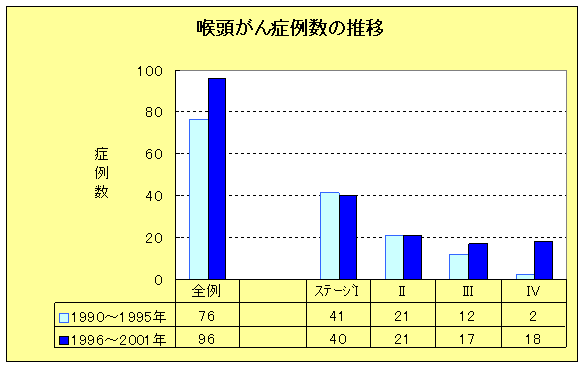
喉頭がんは頭頸部がんの中では早期例が多いのが特徴です。
高齢化に伴い、全体として喉頭がんの増加傾向にあります。
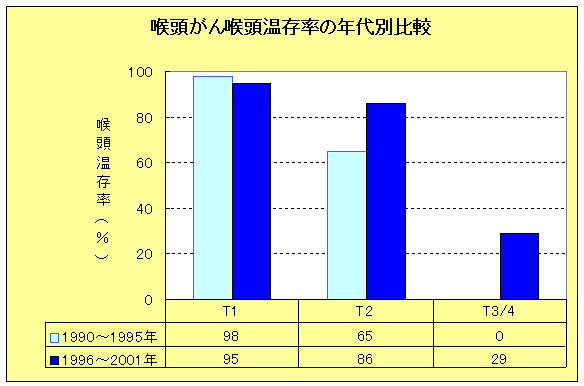
近年、T3/4の進行喉頭がんにおいて化学放射線療法による喉頭の温存が増加しています。
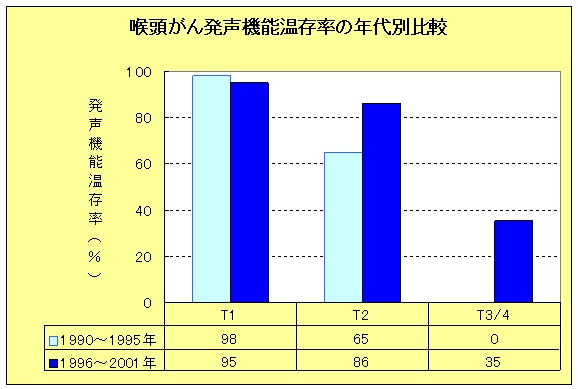
近年、T3/4の進行喉頭がんにおいても化学放射線療法による形態と機能の温存、さらに喉頭部分切除術による機能温存例が増加しています。
食道がん
(消化器外科部)
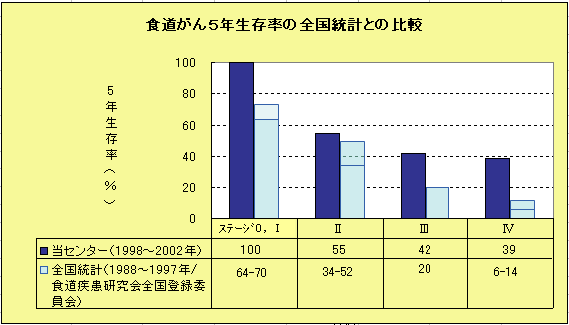
食道がん外科的切除例の5年生存率を当センターと全国統計との比較で示しています。全国統計がやや古いとはいえ、当センターの治療成績は確実に全国平均を大きく上回っていると言えます。現在私たちは、病期Ⅱ~Ⅳの再発率を減少させるために、手術前後の補助療法の開発に取り組んでいます。この研究の成果が現実のものとなれば、さらなる治療成績の向上が期待できると考えられます。
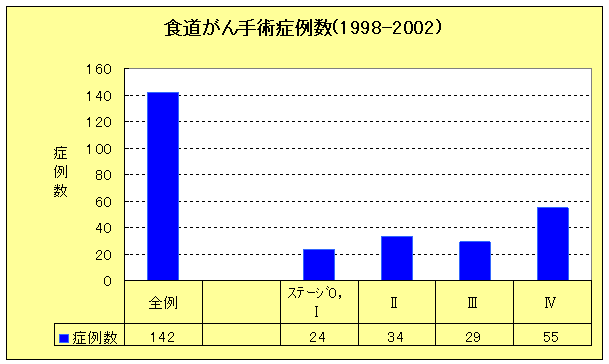
食道がん外科的切除例の病期の内訳を示したものです。食道がんで早期がんと定義されるのは病期0、Ⅰ期で、全体の17%となっています。食道がんはリンパ節転移の有無が治療成績を大きく左右します。リンパ節転移を伴なう病期Ⅱ期の一部とⅢ、Ⅳ期の、いわゆる進行がんが手術例の70%を占めています。この傾向は全国的にもここ20年来変わりがありません。このような現状でも、治療成績は徐々に向上し、当センターでは術後5年生存率は50%を越えるに至っています。参考までに、1988-1997年までの全国集計では、食道がん手術例の5年生存率は36%となっています。
肺がん
(呼吸器外科部)
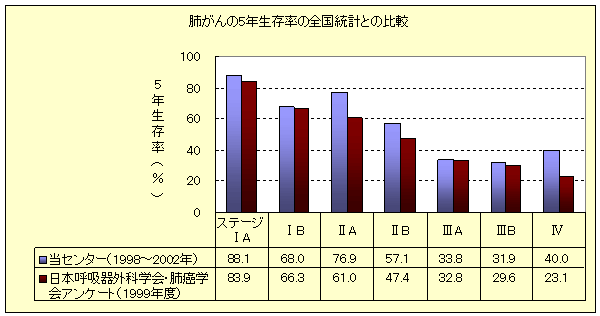
愛知県がんセンターのステージ別5年生存率(1998-2002年)と日本呼吸器学会、肺癌学会合同による全国調査(1999年)との比較を示します。どのステージでみても、当院の手術成績が優れています。
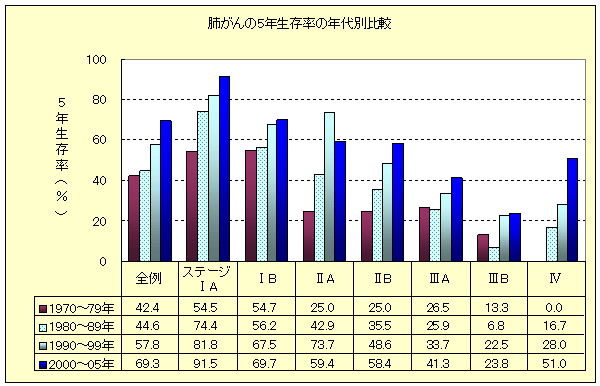
1970年からの手術後の5年生存率の推移を示します。どのステージで見てみても、10年ごとに治療成績が向上していることがよくわかります。
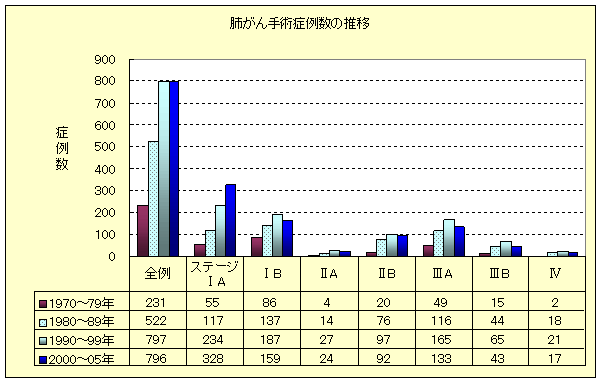
1970年からのステージ別症例数を示します。1970-1989年の20年間の症例数より、2000-2005年の6年間の症例が多いことを見てもわかるように、肺がんの手術症例数は増加しています。とくに、ステージ IAの症例数ののびが顕著です。
胃がん
(消化器外科部)
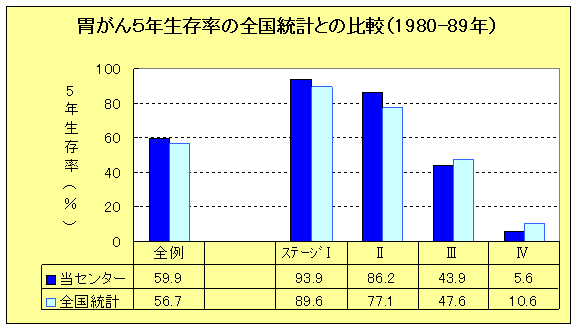
全国統計データは胃癌研究会のデータから消息不明例を除いて計算したものです。消息不明例には死亡例が多く含まれるため、これを除くと成績が向上したように見え、ステージⅢ・Ⅳで当センターの治療成績が悪いように見えるのは、当センターには消息不明例が1例もないからではないかと考えられます。
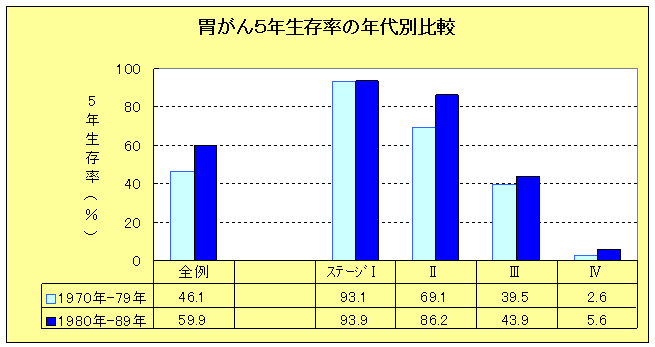
死亡には再発だけではなく、交通事故などのほかの原因での死亡を含んでいます。
もともと再発がほとんどないステージIの生存率は年代別で変わりありませんが、手術技術の進歩によって ステージIIでの生存率の向上が認められます。しかし、有効な抗がん剤がないため、より進行したステージⅢやIVでの生存率は向上した所で僅かに止まっています。
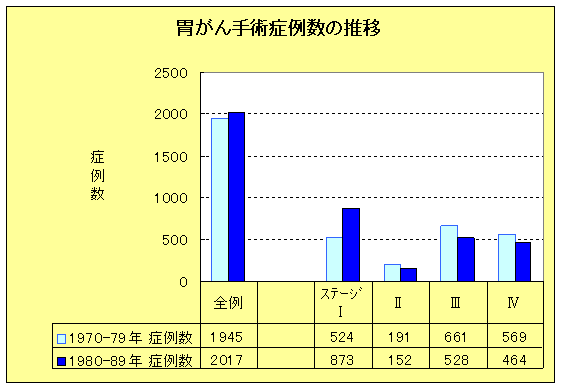
早期発見・早期治療という意識の向上、検診の普及や内科診断医の努力により、早期がんが増えてきた結果、ステージIが増えてきています。
結腸がん
(消化器外科部)
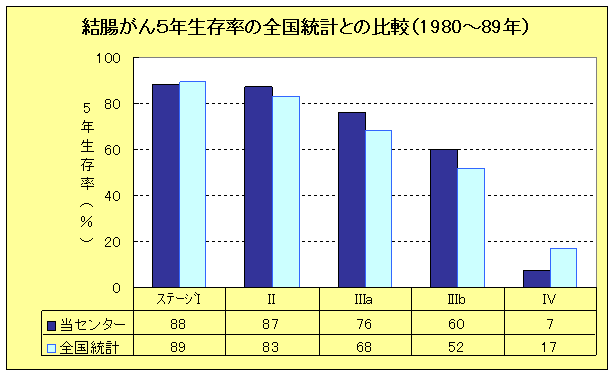
センターの予後調査は生死に関しては消息不明がありませんが、全国登録例は10%以上の消息不明例が存在し、生存率から外されています。したがって比較に関しては同じ母集団ではないことを考えるとほぼ同じ成績と考えるべきでしょう。
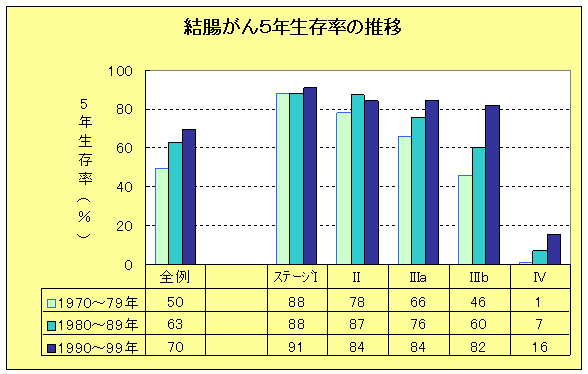
治療の根幹である結腸切除は困難な手術手技ではありませんが、安易な小範囲切除は行わず、十分な腸管切除と過不足のないリンパ節郭清手技の改善、徹底により、リンパ節転移のある症例(ステージIIIa, IIIb)の生存率は、向上しています。一方、リンパ節転移のない症例においては手技の改善による変化は見られていません。遠隔転移を認めるステージIVでは転移巣の積極的切除によりわずかではありますが、改善傾向を認めています。これらの期間での抗がん剤の効果はほとんど同じです。
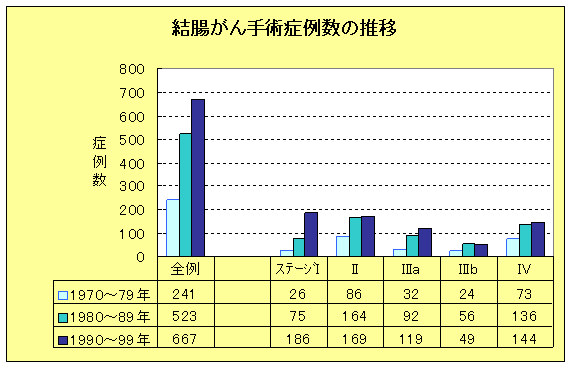
年々大腸がんは増加していますが、その大部分は結腸がんの増加によります。特に便潜血反応や大腸内視鏡の普及により、進行状況としては早い段階でのステージI症例の増加が目立ちます。早い段階で見つかったがんに対しては内視鏡治療、腹腔鏡治療などより低侵襲な治療法の選択が可能です。一方、遠隔転移を認めるステージIVは症例数は増加していますが、割合はほぼ同じです。
直腸がん
(消化器外科部)
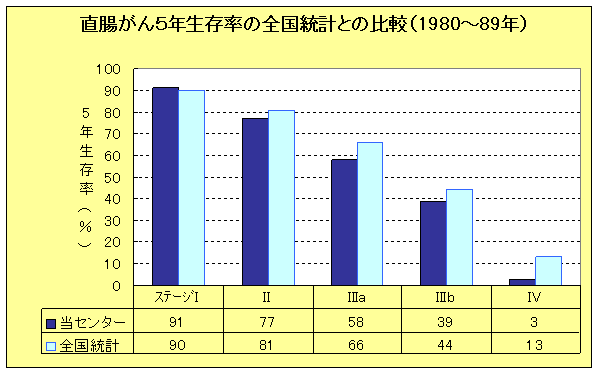
当センターの予後調査は生死に関しては消息不明がありませんが、全国登録例は10%以上の消息不明例が存在し、生存率から外されています。したがって比較に関しては同じ母集団ではないことを考えるとほぼ同じ成績と考えるべきでしょう。
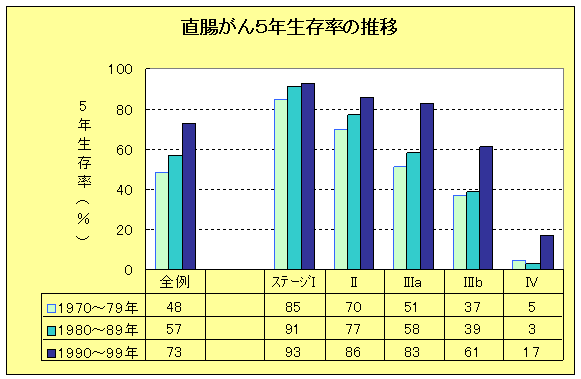
直腸がんは結腸がんに比較すると、その解剖学的複雑さからリンパ節転移のない症例でも骨盤内にがんが遺残しやすく、手術手技の改善、他の治療法の併用が必要でした。十分な腸管切除と、他臓器との剥離面の十分な距離確保、過不足のないリンパ節郭清手技の改善、徹底、場合により放射線治療の併用を行うことでステージ全般的に年次的に改善傾向を認めています。遠隔転移を認めるステージIVでは転移巣の積極的切除によりわずかではありますが、改善傾向を認めています。これらの期間での抗がん剤の効果はほとんど同じです。
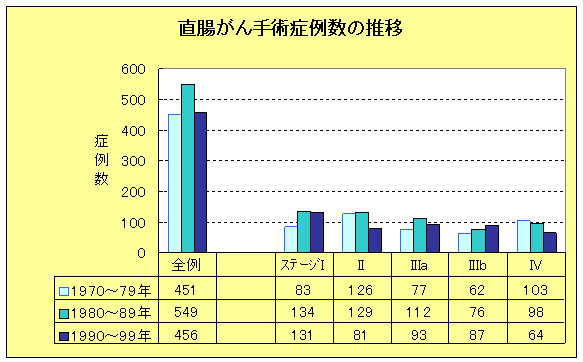
直腸がんの症例数の増加はありません。直腸がんの治療は、人工肛門、排便機能、性・排尿機能障害など後遺症も大いにあり、早期の段階での発見、治療でこれらの後遺症を減らす工夫ができます。特に血便など症状が出現しやすい部位ですからおかしいと思えば医療機関を受診し、がんを否定してもらうことが重要です。一方、リンパ節転移の認められる症例では徹底したリンパ節郭清や術後の放射線治療、補助抗がん剤治療など機能温存を極力図りながらも再発を減少させる努力が行われています。
肝・胆・膵がん
(消化器外科部)
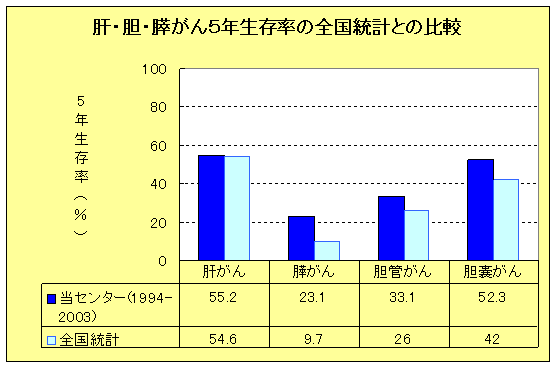
肝、胆道、膵がんともに術後成績は良好で全国統計を上回っています。
<全国統計>
肝がん:日本肝癌研究会2001年
膵がん:日本膵臓学会2002年
胆管がん:日本胆道外科研究会1988-1997年登録
胆嚢がん:日本胆道外科研究会1988-1997年登録
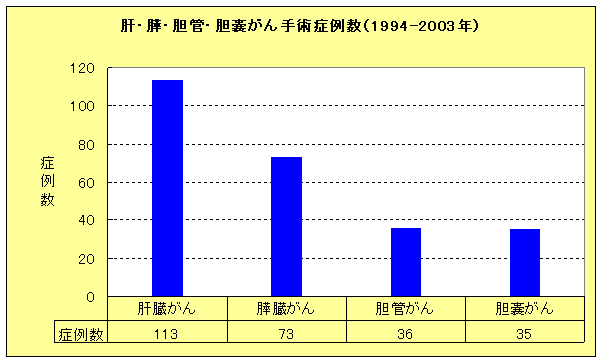
肝、胆道、膵がんともに多数の手術を行いました。
乳がん
(乳腺科部)
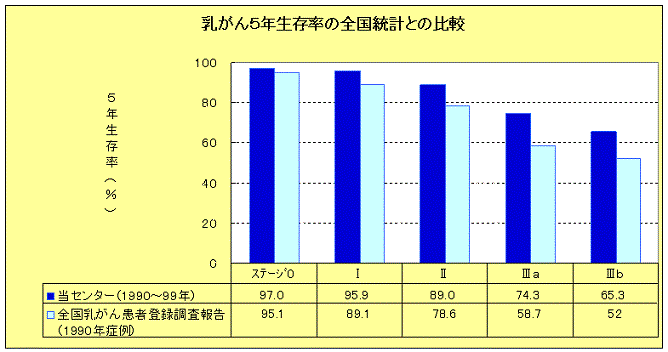
すべてのステージで5年生存率は全国平均を上回っています。当院では世界で標準的な術後の補助療法(薬物療法)を積極的に取り入れていることが原因として挙げらます。また再発後も薬物療法を含めた集学的治療が進み、再発後の生存期間の延長もこのデーターに寄与していると考えられます。
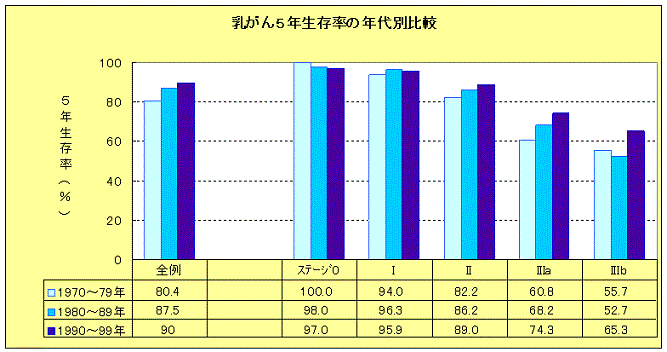
近年の薬物療法の進歩により、術後に補助療法として標準的な薬物療法を行うことが一般化しました。特にステージの進行した症例での5年生存率の改善が顕著なのはこれが原因に挙げられます。
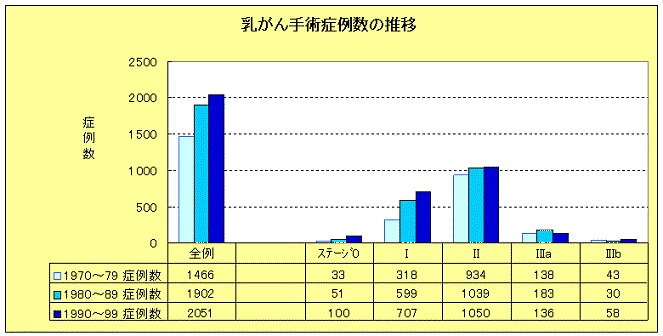
生活の訪米化により日本の乳がん発生率は急速に増加しています。当科でも同様の傾向です。特にステージ0、Ⅰの症例数が増加していますが、これは早期診断に必要な画像診断機器の導入と、それを適格に診断する診断能力の賜物です。今後は、ますますこの傾向は続くと予想されます。
子宮頚がん
(婦人科部)
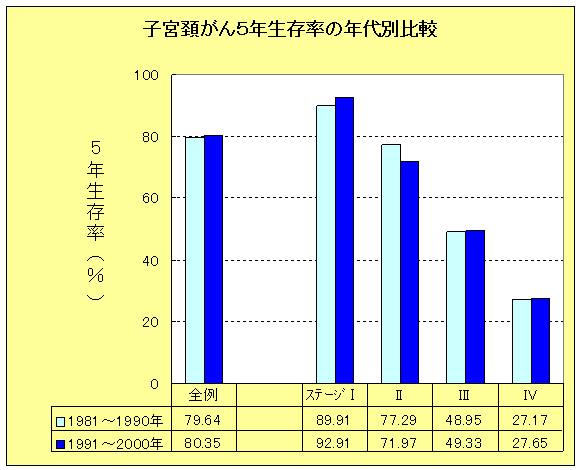
浸潤がんの治療はI 期では手術単独ないし術後放射線治療, II 期では手術+術後放射線治療、I,II 期の手術非適応及びIII,IV期例では放射線治療が標準的治療としてほぼ確立されこれまで行われたてきました。その結果、治療成績はほぼ固定された感があります。予後改善の余地がある主としてII期以上の進行例に対し 近年chemoradiation(化学放射線治療)が導入され今後の予後改善が期待されています。当院においても放射線治療部と共同で積極的に行っており、良好な結果が確認されつつあります。また更に新しい有効な抗がん剤の導入による積極的な治療も行っています。
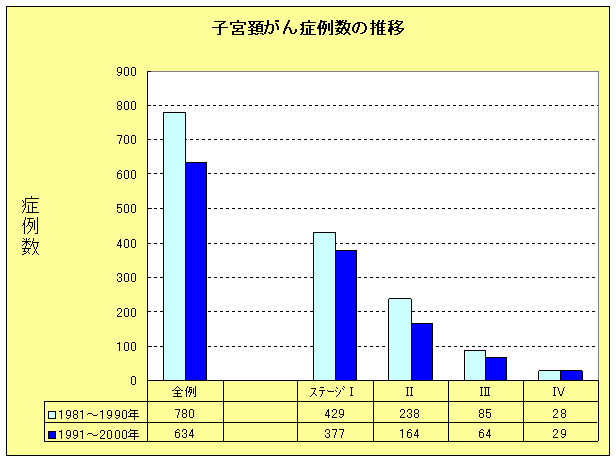
子宮頚がんは減少傾向にあると言われていますが 婦人科がんの中で現在も最も多いがんです。特に近年30才未満の若年者の子宮頚がんが増加してきています。検診の普及により早期発見例が増加してきており 近年では非浸潤がんである0期(上皮内がん)が約半数以上となってきています。従って性交渉に伴う接触出血等の不正出血を認める場合のみならず 20才よりの検診が推奨されます。
子宮体がん
(婦人科部)
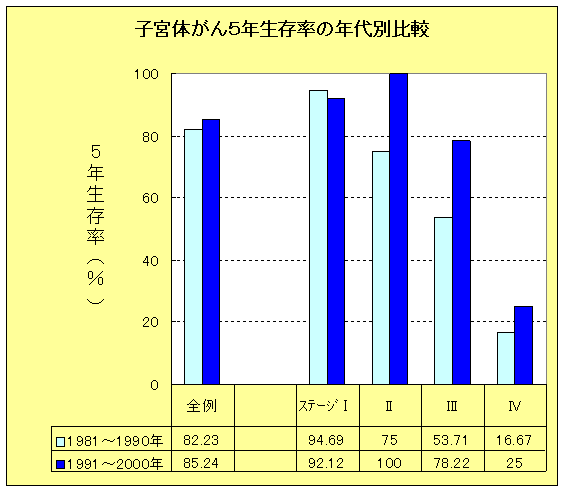
治療は手術が基本で 手術により摘出された子宮、リンパ節、腹腔内細胞診等にてがんの進行期が最終的に診断されます。早期であるI 期の大半は手術のみで治癒が可能であり その5年生存率は変わりませんが、Ic 期以上の進行例では手術後に 主として化学療法による補助療法による集学的治療を行っています。徹底した手術と化学療法の進歩により予後改善が見られます。平成16年度中にはより有効な抗がん剤が保険適応として承認され 広く一般に投与可能となる見込みです。
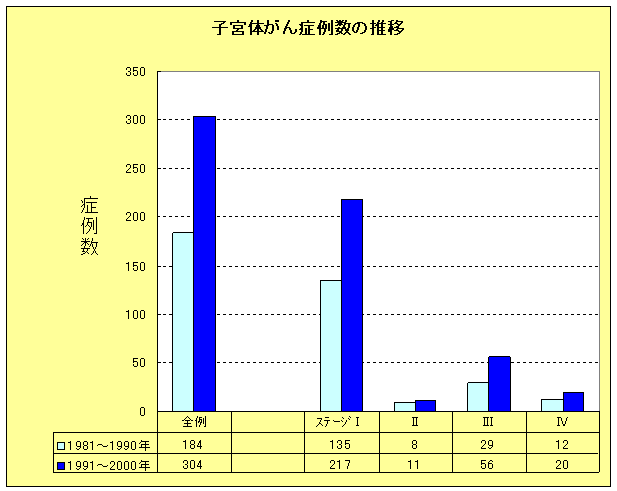
子宮体がんは卵巣がん以上に急速に増加しつつあります。食生活の欧米化がその原因の一つであり、肥満・高血圧・糖尿病は危険因子と考えられています。不正性器出血が主な初期症状で子宮体がんの90%に見られます。特に閉経後や、未経妊・未経産、月経不順女性の不正出血時には子宮体がんの検査が望ましいです。幸い比較的早期の子宮に限局している I 期がんが過半数を占めています。
卵巣がん
(婦人科部)
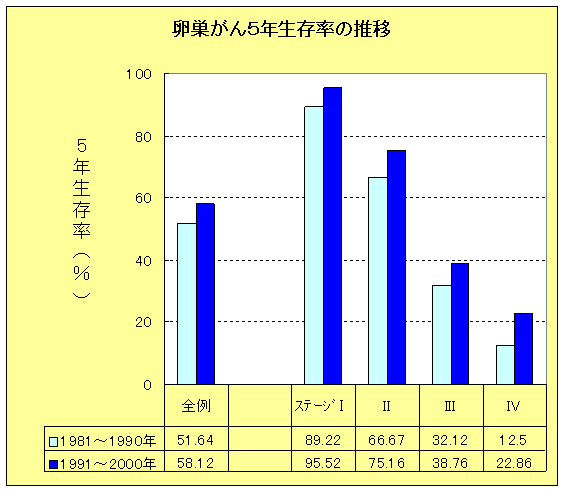
卵巣がんの治療は まず卵巣がんの確定診断と進行期確認に手術が必要となります。卵巣にのみ限局している最も初期のIa期では 手術のみで90%以上の治癒が期待されます。しかし卵巣以外の主として腹腔内、リンパ節に進展している例では 徹底した腫瘍減量手術と化学療法による集学的治療が基本となります。徹底した手術に加え 有効な抗がん剤開発による化学療法の進歩により 進行例での生存率の改善がみられます。しかしまだまだ進行例の予後は極めて不良ながんであり 更に有効な化学療法が検討されています。
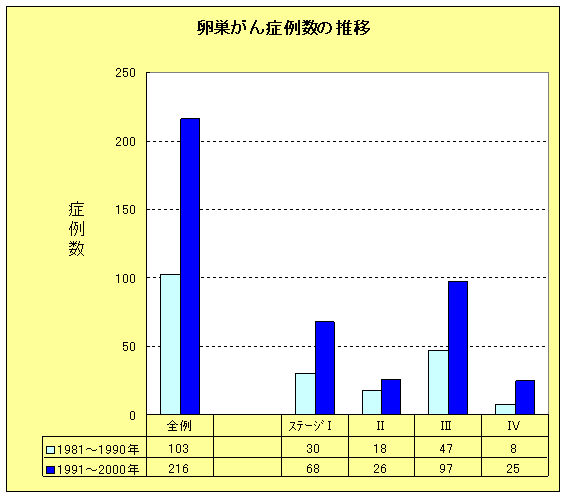
日本での卵巣がんの罹患数は毎年約6,000人と推定され 近年ますます増加しつつあります。卵巣は腹腔内臓器のため 腫瘍が発生しても進行して腹水が貯留するまで自覚症状が乏しく、また適切な検診方法がないことから 約半数はIII/IV期の進行がんとして発見されています。当院での治療例においても同様の傾向が確認されています。
膀胱がん
(泌尿器科部)
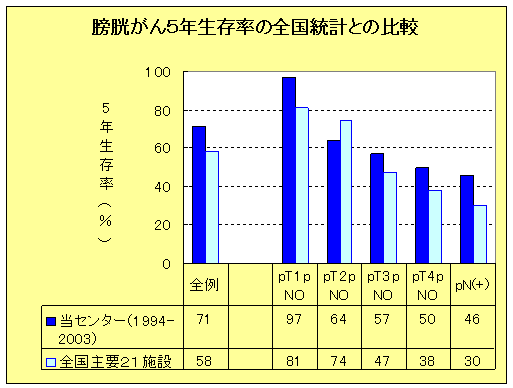
当センターで行った根治的膀胱全摘術を行った治療成績です。pT2の成績が全国主要21施設より低いのは、腺がん・小細胞がん・移行上皮がんGrade3などの悪性度の高い組織型が多かったことが原因と考えています。
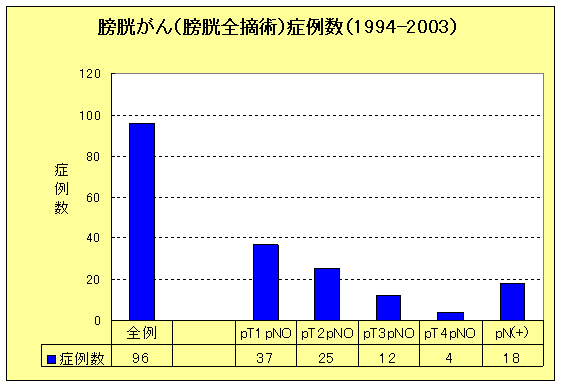
当センターの膀胱がんに対する治療の基本方針は、根治(完全に治す)を優先することです。よって、がんの悪性度が高く(Grade3)、多発性で、膀胱筋層近くまでがんの浸潤を認める場合には、根治的膀胱全摘術を選択する場合もあります。
前立腺がん
(泌尿器科部)
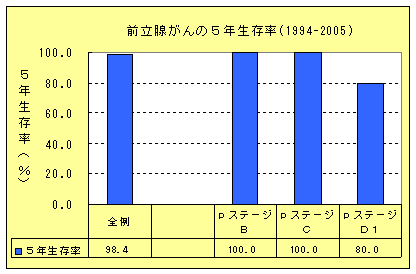
当センターで行った根治的前立腺全摘術の治療成績です。全例の5年生存率は98.4%です。前立腺がんの術前診断(臨床病期の診断)は難しく、過小評価する傾向があります。術後に再発した場合には、通常は内分泌治療を行いますが、当センターでは放射線治療を積極的に行っています。
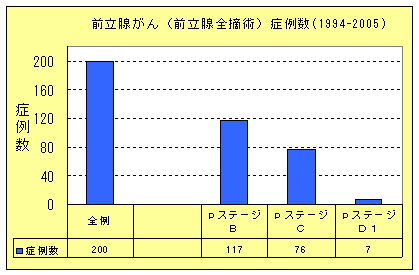
根治的前立腺全摘術の適応は、基本的にはステージBとしていますが、ステージCでも御希望により行っています。また、根治治療として、手術以外にも放射線治療(三次元原体照射法やトモセラピー)を積極的に行っています。
骨悪性腫瘍
(整形外科部)
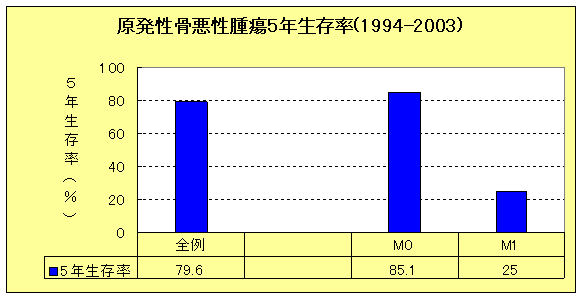
1994年から2003年までに原発性骨悪性腫瘍に対して手術を行った症例における5年生存率は全体で79.6%、遠隔転移のない症例(M0)では85.1%、初診時遠隔転移を呈していた症例(M1)では25.0%です。特に骨肉腫のプロトコールは名古屋大学と連携して行っており、初診時遠隔転移をきたしていない症例における予後は比較的良いが、初診時遠隔転移をきたしていたものではその予後は厳しいものです。現在、このような症例に対して末梢血幹細胞移植を併用した超大量化学療法や分子標的治療としてイマチニブの臨床治験を検討しています。
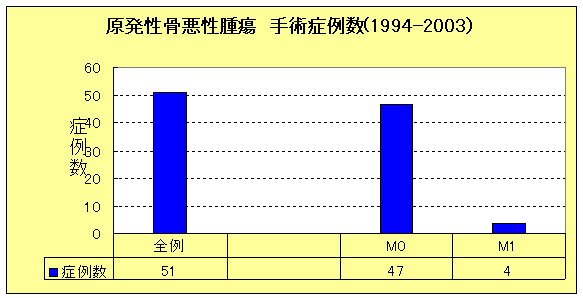
1994年から2003年までに手術を行った原発性骨悪性腫瘍症例の内訳は骨肉腫23例、ユーイング肉腫11例、軟骨肉腫7例、MFH(悪性線維性組織球腫)3例、脊索腫3例、その他4例です。2003年度における骨腫瘍手術は20例でその内、良性6例、悪性14例ですが、局所再発や手術による重篤な合併症は見られていません。今後さらに原発性骨軟部腫瘍のセンターとしての役割を果たしていきたいと考えています。
軟部悪性腫瘍
(整形外科部)
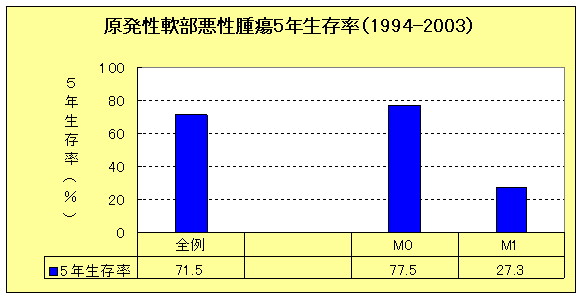
1994年から2003年までに原発性軟部悪性腫瘍に対して手術を行った症例における5年生存率は全体で71.6%、遠隔転移のない症例(M0)では77.5%、初診時遠隔転移を呈していた症例(M1)では27.3%であり、原発性骨悪性腫瘍症例にほぼ近似したデータとなっています。
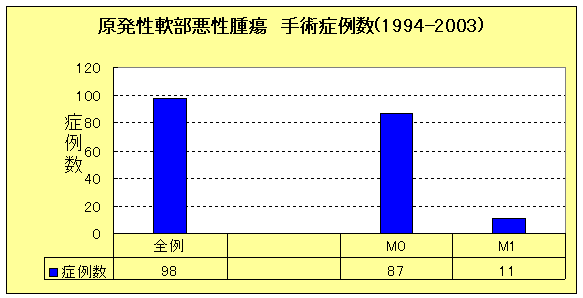
1994年から2003年までに手術を行った原発性軟部悪性腫瘍症例の内訳はMFH(悪性線維性組織球腫)18例、脂肪肉腫14例、滑膜肉腫14例、横紋筋肉腫8例、平滑筋肉腫8例、神経肉腫8例、DFSP(隆起性皮膚線維肉腫)6例、骨外ユーイング肉腫5例、その他17例です。2003年度における軟部腫瘍手術は39例でその内、良性23例、悪性16例ですが、局所再発や手術による重篤な合併症は見られていません。
リンパ腫・白血病・多発性骨髄腫・骨髄異形成症候群
(血液・細胞療法部)
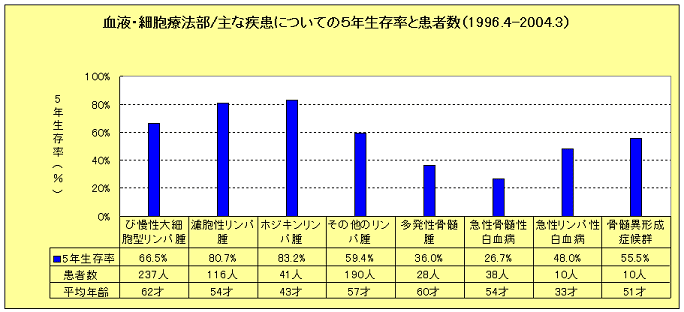
このグラフは当院入院時からの5年生存率です。当センターで診断後治療された患者さんと、他院で再発した後当センターを受診し治療をされた患者さんを含みます。当センターで診断後治療された患者さんの生存率はこの数値より上回ります。また、最近では、よく効く抗がん剤(分子標的治療薬など)の使用が可能になっていますし、また、抗がん剤治療が効きにくい患者さんには自家末梢血幹細胞移植を併用した大量化学療法や同種移植を行っており、このグラフより、さらに良い成績が出ています。
内視鏡検査・治療
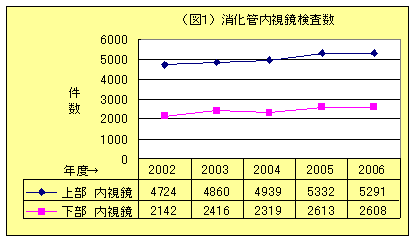
胃内視鏡検査(上部消化管内視検査GIF)(図1):以前にお勧めしていました検診目的の毎年一回のGIFを止め、病院本来の目的である精密検査目的のGIFを主として行うことに致しました。最近5年間のGIF件数は4800から5300件程度であり、漸増しております。紹介患者さんの増加が背景にあるものと思われます。
大腸内視鏡検査(下部消化管内視検査CF)(図1):ドック等で行われた便潜血反応陽性の精密検査希望の患者さんの増加に伴って着実に増加しています。
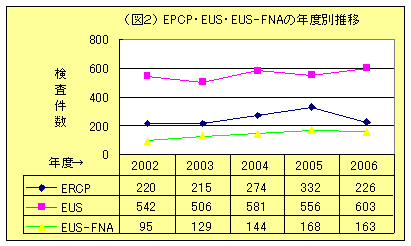
内視鏡的膵胆管造影(ERCP)(図2):非侵襲的的なMRCPの普及により症例数自体は減少していますが、治療目的(胆管ステント)の患者さんや手技的に困難な患者さんの他施設からの紹介の増加が見られます。
超音波内視鏡検査(EUS) (図2):消化器のがんの進展度診断(深さや広がり)、膵・胆道がんの診断に有用な検査ですが、その有用性はがんの内視鏡治療の増加と比例し増加してきました。
超音波内視鏡下穿刺生検(EUS-FBNAB)は通常の内視鏡検査では診断困難な消化管粘膜下腫瘍や膵胆道がんの確定診断には欠くことのできない検査法ですが、検査数の伸び、検査総数ともに全国で有数と自負できます。
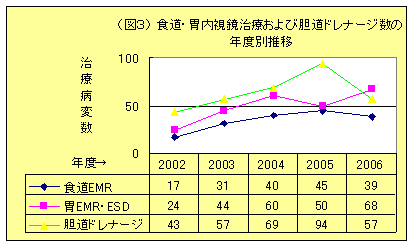
食道がん内視鏡切除(EMR)(図3):食道がんに対する診断能の向上とともに、食道がんに対する当院の評価が高くなり紹介患者さんが増加しました。そのため食道EMRの症例数は着実に増加しており、今後も増加が見込まれます。
胃がん内視鏡切除(EMR・ESD)(図3):胃腫瘍に対する内視鏡治療は、これまで内視鏡的粘膜切除術(EMR)で行っていましたが、一度に切除できる大きさに限界があり、その適応は腫瘍径が約2cmまでの病変に限られていました。しかし内視鏡的粘膜下層剥離術(ESD)の開発に伴い、2cmより大きな病変に対しても治療が可能となってきました。
当院においても2003年よりESDを導入した結果、治療件数が増加しています。最近は紹介される症例も増えており、益々の増加が見込まれます。
胆道ステント(図3):主として手術不能膵・胆道がん患者さんのQOL(生活の質)向上のために視鏡的手技を用いて黄疸のある患者さんに対して行う処置です。化学療法をお受けいただく上記がん患者さんの増加により症例数も着実に伸びています。
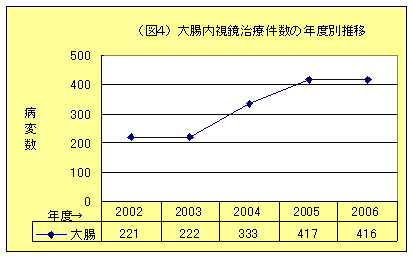
大腸ポリペクトミーおよび内視鏡切除(EMR)(図4):大腸の内視鏡治療は、2001年よりクリニカルパスを導入し安全性を考え全例入院で治療をおこなっています。
最近では、検診でみつかる大腸ポリープや大腸癌の数が増加しており、その内視鏡治療件数も増加しています。また従来では手術を行っていた病変にもESDなどの内視鏡治療を行うようになり、今後益々大腸内視鏡治療件数の増加が見込まれます。
IVR治療
(放射線診断・IVR部)
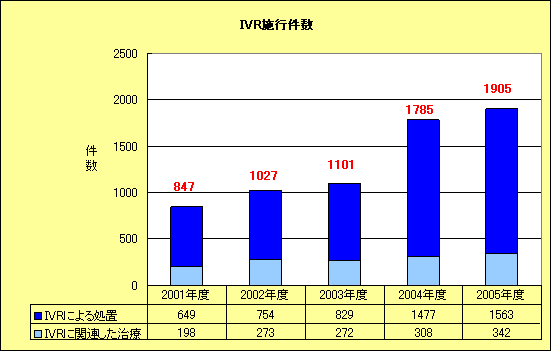
X線透視,CT,超音波といった画像誘導下に針やカテーテルを用いて経皮的に体内へとアプローチし診断または治療を行うインターベンショナルラジオロジー(IVR)はがん診療において一翼を担っており、IVRによる処置は積極的ながん緩和ケアとして認知され、件数は増加しています。当科でのIVRに関連した直接的治療はほとんどが肝悪性腫瘍に対するものであり、肝動脈化学塞栓療法、肝動注化学療法、経皮的凝固療法を行っています。

